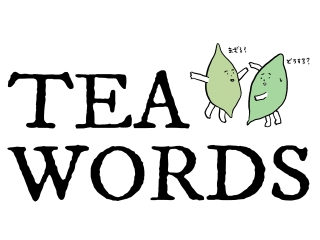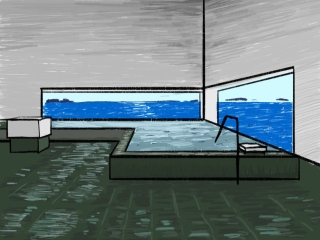nomaになる、茶葉づくり。
2025年4月18日公開
くらしを楽しむことは、旬を楽しむこと。
焙じ茶のさまざまな旬を、丸八製茶場からご紹介します。
今回は、2025年3月15日発売の「焙茶noma(ノマ)」についてです。

「焙茶noma」の花のような香りは、香料を使用せず、茶葉そのものから引き出したものです。その中でも、メインで使用されている「静7132」という茶葉からは、桜の葉のような香りが生まれます。これは「静7132」に含まれる「クマリン」という成分に由来しています。

「焙茶noma」は、温かくいれても、水出しにしてもそれぞれのおいしさを楽しめます。その日の気候や気分に合わせた飲み方を、どうぞ。
「焙茶noma」が生まれる、
朝もやの茶園。
暖かな時間が少しずつ長くなり、街のあちこちでみずみずしい生命の気配が感じられるようになりました。柔らかな風が肌に触れる感触を楽しみながら、屋外で過ごす穏やかな時間。窓を開け、室内に外気を取り込むときに感じる、ほのかな高揚感。はじまりの季節は、なぜかすべての人にワクワクやときめきを運んできます。
「焙茶noma」の「noma」という名前には、人と時間との「間(マ)」を豊かにしたいという想いが込められています。2025年3月15日発売の「焙茶noma」は、芽吹きを思わせる優しい渋味と、花のような香りの余韻の焙じ茶。若々しい草花に包まれているかのような香りが、心軽やかな気持ちにさせてくれます。

「焙茶noma」のパッケージ。季節の高揚感をイメージした色彩は、写真家の北岡稔章さんによる写真。そこに、書家の池多亜沙子さんによる墨象(前衛書道)のモチーフをあしらっています。
日本で生産されているお茶の66.7%は「やぶきた」と呼ばれる品種ですが、残りの約3割の中には、「静7132」をはじめとする香りに特徴のある品種が多く含まれています。そんな希少な品種をいくつも栽培しているのが、静岡県静岡市清水区で茶園 豊好園(ほうこうえん)を営む片平次郎(かたひらじろう)さんです。
今回は、全国茶品評会で1等3席(全国3位)、世界緑茶コンテスト最高金賞を受賞するなど、製茶で大きな成果を上げる傍ら、自身の茶園でお茶の生産を行い、さらに共同製茶工場を活用したお茶づくりも手掛ける片平さんに、お話を伺いました。
お茶の未来を考え、若手生産者が
集まった「茶農家集団ぐりむ」。
「焙茶noma」の原料である「静7132」の生産者である片平次郎さんは、代々伝わる茶園「豊好園」を営んでいます。「実は、今回の丸八製茶場さんの『静7132』には、豊好園だけではなく、ぐりむという茶農家集団の茶葉も含まれているんです」と語ります。
ぐりむは、片平さんを含む同じ地区の若手生産者によって生まれた会社です。「ぐりむの共同製茶工場では、大量のお茶を製茶することができます。お茶を収穫する量は、その日に製茶できる量から逆算して考えます。なので、製茶工場があると製茶できる量が増え、ベストな状態で摘み取ることができる茶葉が多くなるんです」

茶農家集団ぐりむのメンバー。今回お話をうかがったのは、後列右の片平次郎さん。受け継いだ「豊好園」を営みながら、ぐりむの運営も行います。他のメンバーも、それぞれ自身の茶園を持っています。
また、ぐりむでは、耕作放棄された茶畑の再生も行っています。「できる範囲で、ですが。お茶の生産者、大きくはお茶の未来をつくっていくのは僕たちです。そのためにも、さすが静岡県、お茶どころだよね!という美しい景色を残していきたいんです」

ぐりむの共同製茶工場がある静岡県静岡市清水区にある両河内。山の斜面に美しく広がる茶畑は、この地域の生産者が守り続けてきたもの。
「ペットボトルのお茶の登場によって、お茶づくりに均一な味が求められるようになりましたが、この地域の傾斜地では大量生産は難しいし、何よりそういったお茶づくりに魅力を感じないんです」という片平さん。「静7132」のような希少な品種をつくる背景には「わかりやすい旨味、アミノ酸の味ではない、香りのお茶の需要が増えていると感じます」という、お茶の最前線にいらっしゃる肌感覚があるようです。
チャの樹の個性と向き合いながら
手間をかけて育てる「静7132」。
「『静7132』は枝が暴れるんですよね。癖があるんです」と、片平さん。「育つ過程で、チャの樹の枝を剪定する工程があります。すると、そこからいい具合に枝が分岐していく。でも『静7132』は、『やぶきた』よりも多めに手を入れないと、芽が増えずに育ってしまい、収量が減ってしまう」
そういったチャの樹の個性は、長い時間をかけて試行錯誤を繰り返しながらつかんでいくもの。加えて、昨今の気候変動もあり、毎年同じ茶葉を同じように生育することは困難になっています。その中で高い品質を維持した茶葉を出荷できるのは、まさに片平さんのような生産者の方の日々の努力があってこそです。

ほんのりとピンク色に色づく「静7132」の新芽。「この状態になるのは数日だけ。すぐに色は消えてしまいます」と片平さん。
「『静7132』のおもしろいところは、ごく数日の間ですが、新芽がピンク色に染まるところですね。その時期、茶園の『静7132』のエリアはうっすらと赤く見えます。手でチャの芽を触ると、新茶の香りと共にクマリンの香りもします」
お茶を愛する生産者が、目をかけ、手をかけて育てた「静7132」の茶葉は、丸八製茶場でブレンドされ、幾度にも渡って焙煎を調整し、「焙茶noma」となってお客様のもとへ届きます。

「焙茶noma」の茶葉。「静7132」をはじめとする茶葉を、浅い焙煎で仕上げました。ふっくらとふくらんだ茶葉からは、花のような香気と共に、焙じ茶ならではの芳ばしい香りが漂います。
「焙茶noma」をはじめとした、香りに特徴のあるお茶を丸八製茶場がつくることができるのは、片平さんのような新しい試みにワクワクしながら一緒に挑戦してくださる生産者の存在があってこそ。今回のインタビューでも、片平さんと丸八製茶場の製造部門の担当者がお茶談議に花を咲かせる場面がありました。
新しいことに挑戦したくなるこの時季。心が浮き立つような味と香りのお茶で、どうぞ、お茶のワクワクするような未来に想いを馳せてみてください。